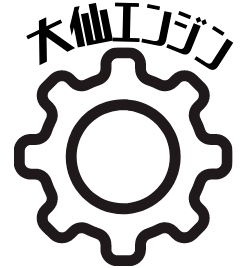村おこしボランティアで大仙市を訪れた学生たちに、10日間の農業やイベントでのボランティアや交流を通じた「関係」の中で、もっと話を聞いてみたいと思った人を、村おこし活動として取材してもらいました。

ーー簡単な経歴について教えてください。
秋田県大仙市で生まれ、地元の小・中・高校を卒業後、新潟の大学で空間や街づくりについて学びました。現在は両親が営む生花店で働き始めて3年目です。
花屋の仕事と並行して「kireine」のプロジェクトを進めながら、地域の活動にも積極的に参加しています。
ーーどうして観賞用の稲「kireine」を始めたのですか?
父が10年前、大仙市で開発された観賞用稲の販売に関わっており、その美しさが当時小学生だった私の心に強く残っていました。
ところが大学時代に、観賞用稲がすでに扱われていないことを知り、「もう一度広めたい」と思うようになりました。そこでご縁のあった農家さんに相談し、農地の一角をお借りして観賞用稲を育てさせていただけるようになったのが始まりです。
ーー優花さんの考える大仙市の魅力はなんですか?
景色の美しさはもちろん、耳に届く音や草花の香りなど、四季折々の変化を五感で感じられるところです。そうした日々の変化が、暮らしの中で刺激となっています。
大学時代に一度大仙市を離れたことで、改めて大仙市ならではの魅力に気付くことができました。
ーー大学卒業後、大仙市に戻ろうと思ったのはなぜですか?
観賞用稲に取り組むと決めたこと、そして花屋の仕事にも挑戦してみたいと思ったことが大きな理由です。
ーー「kireine」に対する思いを教えてください。
秋田で暮らす中で、田んぼの稲が少しずつ実っていく姿に美しさを感じてきました。「食べて美味しい」というだけではなく、稲そのものの魅力を伝えていきたいと思っています。
また、現在は耕作放棄地が増え、農地の担い手も不足しています。観賞用稲が広まることで、食用稲以外の新たな田んぼの活用方法のひとつになればと考えています。
ーー「kireine」を進めていく中で、「やってよかった」と思う瞬間はありますか?
やっぱり喜んでいただける瞬間が一番嬉しいです。
観賞用の稲を見たことがない方も多いので、最初はどんな反応が返ってくるのか想像できませんでした。私と同じように魅力を感じてもらえるのか不安でしたが、まわりから「かわいい」「きれい」と言っていただけると、「やってよかったな」と実感します。
ーー反対に、大変だと感じることはありますか?
今まで農業に関わる機会がなかった分、稲は身近な存在ではなく、手探りで進めていかなければならないのが大変です。
例えば、稲の管理ひとつをとっても「どこで、どのような状態で保管するか」「どんなパッケージで届ければ、きれいな状態でお客様に届けられるか」など、さまざまなことに配慮する必要があります。
最適な方法を探している途中ですが、最後は自分が「何をしたいか」が一番大切だと思っています。
ーーこれからの夢や目標を教えてください。
「観賞用の稲」という存在の魅力を、もっと多くの人に伝えていきたいと思っています。同時に、このプロジェクトをひとつの事業として確立することも目標です。
地域によって育つ稲の種類は異なるので、さまざまな地域に広まっていけば、それぞれの土地ならではの稲を楽しんでもらえるのではないかと思っています。
ーー最後に一言お願いします。
観賞用の稲をどこかで見かけた際には、ぜひ近くでじっくり見ていただきたいです。そして、もし気に入っていただけたら、ご自宅に飾って楽しんでもらえると嬉しいです。